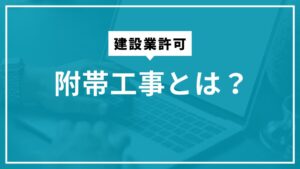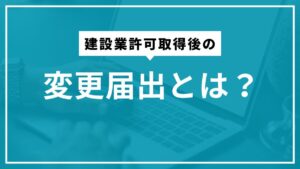個人事業主の建設業許可申請│取得要件・必要書類を解説
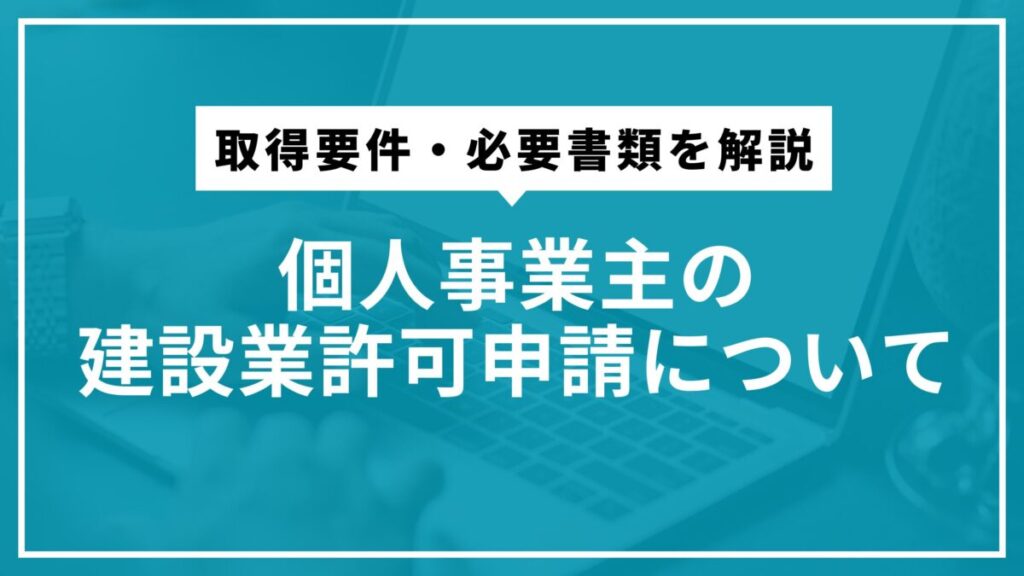
建設業を営む個人事業主の皆さま、こんなお悩みはありませんか?
「元請けから建設業許可を取得するように言われた」「許可がないと大きな工事を受注できない…」
建設業許可は、法人だけでなく個人事業主も取得可能です。取得することで、500万円以上の大規模な工事を受注できるようになり、事業拡大の大きなチャンスにつながります。
この記事では、個人事業主が一般建設業の建設業許可を取得するために必要な6つの要件と、具体的な申請書類について、岩手県での申請を中心にわかりやすく解説します。
建設業許可取得の6つの要件
建設業許可を新規取得するためには、以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。
要件1:経営業務の管理を適正に行う能力があること
事業の経営を総合的に管理・執行した経験を持つ人を配置する必要があります。
必要な経験年数は以下のとおりです。
ケース1~3:「個人」で要件を満たす場合
| ケース | 必要な経験 | 経験年数 |
|---|---|---|
| 1 | 建設業に関し、経営業務の管理責任者としての経験 | 5年以上 |
| 2 | 建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位での経営管理経験 | 5年以上 |
| 3 | 建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位での補佐業務の経験 | 6年以上 |
ケース4・5:「組織」として要件を満たす場合
ケース1~3は個人で要件を満たす場合。4、5は組織で要件を満たす場合です。
| ケース | 常勤役員等の要件 | 補佐者の要件 |
|---|---|---|
| 4 | ・建設業での役員等経験:2年以上 ・上記を含め、役員等または役員等に次ぐ職制上の地位での建設業の経験 (財務・労務・運営のいずれか):5年以上 | 以下の業務経験を各5年以上有する補佐者をそれぞれ配置 (1)財務管理 (2)労務管理 (3)運営業務 ※1人が複数の経験を兼ねることも可能 |
| 5 | ・役員等(建設業以外を含む)としての経験:5年以上 ・上記を含め、建設業での役員等経験:2年以上 | 以下の業務経験を各5年以上有する補佐者をそれぞれ配置 (1)財務管理 (2)労務管理 (3)運営業務 ※1人が複数の経験を兼ねることも可能 |
要件2:営業所に営業所技術者を配置すること
許可を受けたい建設業の種類ごとに、営業所に常勤し、その業務に専念する営業所技術者(専任技術者)を配置する必要があります。
この営業所技術者は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 指定学科卒業+実務経験
許可業種に応じた指定学科を卒業し、高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験があること - 10年以上の実務経験
指定学科を卒業していない場合でも、許可を受けたい建設業に関して10年以上の実務経験があること - 国家資格
技術士、建築士、施工管理技士などの国家資格を取得していること
個人事業主ご自身が、「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」を兼ねることも可能です。ただし、この場合、原則として同一の営業所内に限られます。
一般建設業の「営業所技術者」の資格要件一覧
| 資格区分 | 学歴・資格 | 実務経験年数 | 追加条件・備考 |
|---|---|---|---|
| 指定学科修了者 | 高校卒業 | 5年以上 | 在学中に指定学科を修了していること |
| 大学(短大等)卒業 | 3年以上 | 在学中に指定学科を修了していること | |
| 専門学校卒業 | 5年以上 | 在学中に指定学科を修了していること | |
| 専門学校卒業 (専門士・高度専門士) | 3年以上 | 在学中に指定学科を修了し、専門士または高度専門士の称号を有すること | |
| 実務経験者 | 学歴不問 | 10年以上 | 許可を受けようとする建設業に係る建設工事の実務経験 |
| 国家資格者 | 1級国家資格保有者 | なし | 建設業に関連する国家資格(1級) |
| 2級国家資格保有者 | なし | 建設業に関連する国家資格(2級) | |
| 複数業種経験者 | 学歴不問 | 規定による | 複数業種に係る実務経験を有する者として認められる者 |
| 技術検定合格者 | 1級1次検定合格者 (○○技士補) | 3年以上 | 大学(短大等)指定学科卒業者と同等扱い ※指定建設業7業種・電気通信工事業は適用除外 |
| 2級1次検定合格者 (○○技士補) | 5年以上 | 高校指定学科卒業者と同等扱い ※指定建設業7業種・電気通信工事業は適用除外 |
要件3: 適正な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険、雇用保険に関して、適用事業所に該当するすべての営業所で、必要な届出を提出している必要があります。
個人事業所の社会保険加入義務
個人事業所の場合、従業員の人数によって加入しなければならない社会保険が異なります。
- 従業員が5人以上いる場合
健康保険、厚生年金保険、雇用保険のすべてに加入する必要があります。 - 従業員が1人〜4人の場合
雇用保険には必ず加入しなければなりません。
健康保険と厚生年金保険は、加入しなくても問題ありません。 - 事業主と一人親方のみで働いている場合
原則として、どの社会保険にも加入する必要はありません。
ただし、一人親方であっても、形式上は請負でも実態として労働者と認められる場合は、会社が加入する保険に加入させる必要があります。
建設業許可申請の際に必要となる証明書類等は以下のとおりです。
| 保険の種類 | 加入・納付方法 | 必要な証明書類 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 | 年金事務所に加入 | ・ 直近の保険料領収証書の控え (口座振替の場合は保険料納入告知額・領収済額通知書の控え) ・「社会保険料納入証明(申請)書」 ・「社会保険料納入確認書」 ・「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」 |
| 組合管掌健康保険に加入 | ・健康保険組合の保険料領収証書の控え ・年金事務所発行の厚生年金保険料領収証書の控え | |
| 建設業に係る国民健康保険組合に加入 | ・国保組合が発行した加入証明書の原本 ・年金事務所発行の厚生年金保険料領収証書の控え | |
| 雇用保険 | 自社で申告・納付 | ・労働保険概算・確定保険料申告書」の控え (受付印があるもの) ・領収済通知書の控え |
| 口座振替で納付 | ・「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え ・「労働保険料等振替納付のお知らせ」の控え | |
| 労働保険事務組合に委託 | ・事務組合発行の領収書の控え (労働保険番号が記載されていない場合は、番号がわかる書類も必要) | |
| 上記書類がない場合 | ・届出書の控え(受付印があるもの)など、提出したことを確認できる書類 |
要件4:誠実性があること
個人事業主ご自身や、支配人などの使用人が、請負契約に関して不正や不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。
- 不正な行為とは?
請負契約の締結または履行の際に、詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為を指します。 - 不誠実な行為とは?
工事内容や工期などについて、請負契約に違反する行為を指します。
つまり、許可を受けようとする個人事業主ご自身や、支配人などの使用人が、過去に建設工事の請負契約に関して上記のような法令違反や契約違反の履歴がなく、今後もそのような行為をするおそれがないと判断されることが、誠実性の要件を満たすうえで必要となります。
要件5:財産的基礎・金銭的信用があること
一般建設業許可を取得する個人事業主には、請負契約を適切に履行できるだけの財産的基礎または金銭的信用があることが求められます。
具体的には、以下のいずれかを満たす必要があります。
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 自己資本が500万円以上 | 以下の計算式で求められる自己資本の額が500万円以上であること。 (期首資本金 + 事業主借勘定 + 事業主利益) - 事業主貸勘定 + 利益留保性の引当金および準備金 |
| 500万円以上の資金調達能力 | 担保となる不動産などを有し、取引金融機関から500万円以上の預金残高証明書または融資証明書を取得できること。 |
| 継続営業の実績 | 許可申請前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること。 |
確認資料に関する注意点
| 状況 | 必要な確認資料 |
|---|---|
| 自己資本が500万円未満 (過去5年の継続営業実績がない場合) | 500万円以上の預金残高証明書または融資証明書の提出が必要です。 |
| 事業開始後、決算期が未到来 | 500万円以上の預金残高証明書または融資証明書が必須です。 |
証明書の要件
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 発行日 | 申請受理前1ヶ月以内に発行されたものであること。 |
| 複数の証明書 | 複数の金融機関の預金残高証明書を提出する場合、すべて同日の日付であること。 |
| 合算 | 預金残高証明書と融資証明書を合算することはできません。 |
| 判断基準 | 原則として、申請時の直前の決算期における財務諸表(貸借対照表、損益計算書)に基づいて判断されます。 |
要件6:欠格要件に該当しないこと
虚偽申請、過去の許可取消など、法律で定められた欠格要件に当てはまらないことが必要です。
個人事業主の欠格要件は、申請者本人および建設業法施行令第3条に規定される使用人について判断されます。
一般建設業許可における欠格要件一覧
| 項目 | 欠格要件の内容 | 期間・条件 |
|---|---|---|
| 1. 虚偽記載・重要事実欠落 | 許可申請書やその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている場合 | - |
| 2. 破産手続開始の決定 | 破産手続開始の決定を受けて、まだ復権していない者 | 復権まで |
| 3. 許可取消し (不正取得・営業停止処分違反) | 不正な手段で建設業許可を受けた、または営業停止処分に違反したことにより許可を取り消された者 | 取消しの日から5年間 |
| 4. 廃業届出 (許可取消し逃れ目的) | 許可の取消し処分を免れる目的で廃業の届出を行った者<br>・政令で定める使用人であった者も含む | 届出の日から5年間 |
| 5. 営業停止期間中 | 建設業の営業の停止を命じられた者 | 停止期間中 |
| 6. 営業禁止期間中 | 許可を受けようとする建設業について営業を禁止された者 | 禁止期間中 |
| 7. 禁錮以上の刑 | 禁錮以上の刑(懲役刑など)に処せられた者 | 刑の執行終了日または執行を受けることがなくなった日から5年間 |
| 8. 特定法律違反による罰金刑 | 以下の法律違反により罰金刑に処せられた者 ・刑法(詐欺、脅迫、横領、文書偽造など) ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 ・暴力行為等処罰に関する法律 ・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法 ・労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、職業安定法 ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律など | 刑の執行終了日または執行を受けることがなくなった日から5年間 |
| 9. 暴力団員等 | ・暴力団員 ・暴力団員でなくなった者 ・暴力団員等がその事業活動を支配している場合 | 暴力団員でなくなった日から5年間 |
| 10. 心身の故障 | 精神の機能の障害により、建設業を適正に営む上で必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことができない者 | - |
| 11. 法定代理人の欠格要件該当 | 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合で、その法定代理人が上記のいずれかの欠格要件に該当するとき | 法定代理人の欠格要件に準じる |
個人事業主の新規許可申請に必要な書類
個人事業主が建設業許可(一般・知事)を申請する際に必要な主な書類は、以下のとおりです。
様式は岩手県庁のホームページからダウンロードすることができます。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 建設業許可申請書(様式第一号) | |
| 営業所一覧表(別紙2(1)) | 主たる営業所のほか、従たる営業所がある場合は全て記載 |
| 専任技術者一覧表(別紙4) | 各営業所の専任技術者を記載 |
| 工事経歴書(様式第二号) | 直前の事業年度の主な完成工事を記載 |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号) | 実績がない場合でも作成が必要 |
| 使用人数(様式第四号) | 技術関係および事務関係の使用人数を記載 |
| 誓約書(様式第六号) | 欠格要件に該当しないことを誓約 |
| 常勤役員等証明書(様式第七号)および略歴書 | 申請者(個人事業主本人)の経営業務の経験を証明 |
| 専任技術者証明書(様式第八号) | 営業所の専任技術者の資格等を証明 |
| 実務経験証明書(様式第九号) | 実務経験を要件とする場合に提出 |
| 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号) | 支配人等がいる場合に提出 |
| 許可申請者の住所、生年月日等の調書(様式第十二号) | 個人事業主本人および法定代理人について作成 |
| 財務諸表(個人用:様式第十八号・第十九号) | 新規開業で決算期未到来の場合は不要 |
| 納税証明書 | 事業税(県税)の納税証明書 |
| 営業の沿革(様式第二十号) | 創業からの沿革、建設業の登録および許可の状況、賞罰などを記載 |
| 預金残高証明書または融資証明書 | 新規開業の場合、自己資本要件のために必要 |
| 商業登記簿謄本 | 支配人を置いた場合のみ提出 |
| 営業所の写真 | 建物の全景、主な執務室の状況などが確認できる写真 |
建設業許可申請の注意点とよくある質問
Q. 申請先はどこ?
主たる営業所の所在地を管轄する都道府県庁の建設業許可担当窓口(広域振興局、土木センターなど)に持参して提出します。
Q. 申請手数料はいくらかかる?
新規許可申請(一般・知事)で90,000円かかります。岩手県収入証紙で納付します。
Q. 許可が下りるまでの期間は?
申請から許可までは、おおむね1ヶ月程度かかります。書類に不備があるとさらに時間がかかるため、事前にしっかり準備しておくことが大切です。
Q. 個人事業主から法人に変わった場合は?
法人成りした場合や、事業主の死亡により配偶者や子が事業を引き継ぐ場合には、新たな建設業許可の申請が必要になります。
個人事業主の許可は廃業届を提出し、新たな法人または個人として、改めて申請手続きを行いましょう。
まとめ

建設業許可を取得すれば、500万円以上の大型工事を受注できるようになり、事業拡大の大きなチャンスにつながりますます。
必要な書類を適切に準備し、スムーズな許可取得を目指しましょう。
岩手・盛岡の建設業許可は金子行政書士事務所にお任せください!
当事務所では、お忙しいお客様に代わって必要書類の作成から許可行政庁との調整、申請手続きまでを一貫してサポートいたします。
「自分は許可が取れるのか?」「どの業種で申請すればいい?」「費用はいくらかかる?」など、どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
新規許可申請代行ページ>>