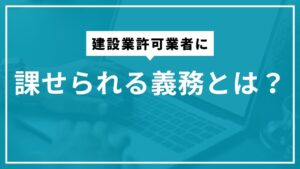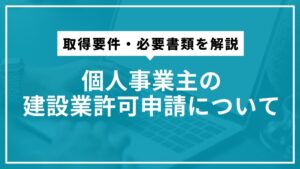建設業許可の附帯工事とは?具体例や請負う際の注意点を解説
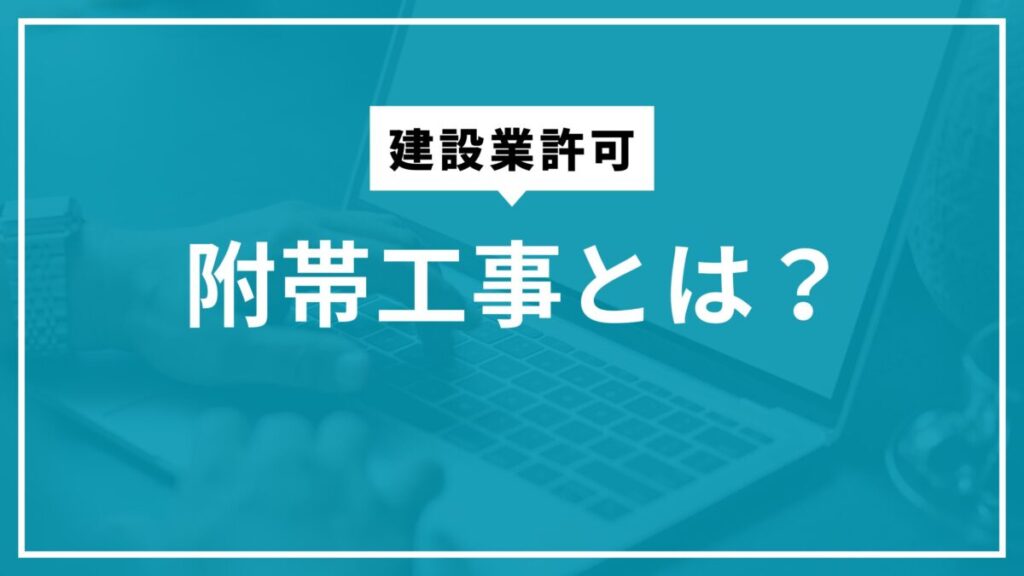
建設業を営む皆さま、日々の業務で「附帯工事」という言葉を耳にすることがあるかと思います。これは、メインとなる工事(本体工事)に付随して発生する工事のことで、建設業許可制度において非常に重要な意味を持ちます。附帯工事のルールを正しく理解していないと、思いがけないトラブルに発展する可能性もあります。
この記事では、附帯工事の定義や具体的な例、そして施工する際の注意点について、建設業許可の観点からわかりやすく解説します。
附帯工事とは?建設業許可における定義と具体例
附帯工事とは、特定の建設業の許可を持っている業者が、本体工事に付随して請け負うことのできる、他の種類の工事を指します。
このルールは、発注者の利便性を高めるために設けられました。たとえば、一つの工事で複数の業者を手配する手間を省くため、関連性の高い工事であれば、許可を持っていない業種の工事でも一括して請け負うことが可能になります。
ただし、無許可で大規模な工事ができてしまうことを防ぐため、附帯工事を請け負う際にはいくつかの条件が設けられています。
附帯工事の具体例
電気工事の付帯工事
電気工事業の許可を持つ業者が、ビルの電気配線改修工事(本体工事)を請け負ったとします。このとき、配線の工事に伴って壁や天井に加工が必要になったり、工事後に壁紙を張り替えたりする作業が発生することがあります。
この壁紙の張り替え作業は、内装仕上げ工事にあたり、附帯工事として一括で請け負うことができます。
水道施設の附帯工事
水道施設工事業の許可を持つ業者が、道路の下に水道管を埋設する工事(本体工事)を請け負う場合、水道管の設置後には道路を元の状態に戻す必要があります。
この道路を元通りにする作業は、舗装工事にあたり、附帯工事として請け負うことが可能です。
附帯工事を請け負う際の注意点
附帯工事を自社で施工する場合、特に注意が必要なのが請負代金の額です。
附帯工事の請負代金が500万円以上(消費税を含む)となる場合、その工事を自社で施工するには、特定の条件を満たさなければなりません。
500万円以上の附帯工事を施工する条件
附帯工事の請負代金が500万円以上となる場合、以下のいずれかの対応が必要です。
- 附帯工事の技術者を自社で配置する
本体工事だけでなく、附帯工事にあたる工事の許可を受けるために必要な技術者を自社で雇用し、現場に配置する必要があります。 - 附帯工事の許可を持つ業者に下請けに出す
自社に技術者がいない場合は、附帯工事の業種において建設業の許可を持っている別の業者に、その工事を下請けに出す必要があります。
※上記のルールは一般的な例であり、実際の契約内容や工事によっては異なる場合があります。判断に迷う場合は、許可行政庁に相談することをおすすめします。
まとめ
附帯工事は、発注者の利便性を高めるための重要な制度です。しかし、そのルールを正しく理解していなければ、許可のない工事を請け負ってしまい、法律違反となる可能性もあります。
附帯工事の請負代金が500万円以上になる場合は、特に注意が必要です。適切な技術者の配置や下請け業者の選定を行うことで、安心して工事を進めることができます。判断に迷うことがあれば、必ず許可行政庁に相談し、適切な手続きを踏むようにしましょう。
岩手・盛岡の建設業許可は金子行政書士事務所にお任せください!
当事務所では、お忙しいお客様に代わって必要書類の作成から許可行政庁との調整、申請手続きまでを一貫してサポートいたします。
「自分は許可が取れるのか?」「どの業種で申請すればいい?」「費用はいくらかかる?」など、どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
▼法令はこちら
建設業法第4条
(附帯工事)
第四条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
建設業法第26条の2第2項
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条の二 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
2 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)