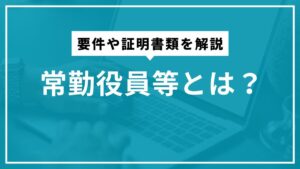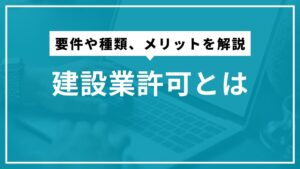営業所技術者とは?特定営業所技術者との違いや兼務の特例を解説
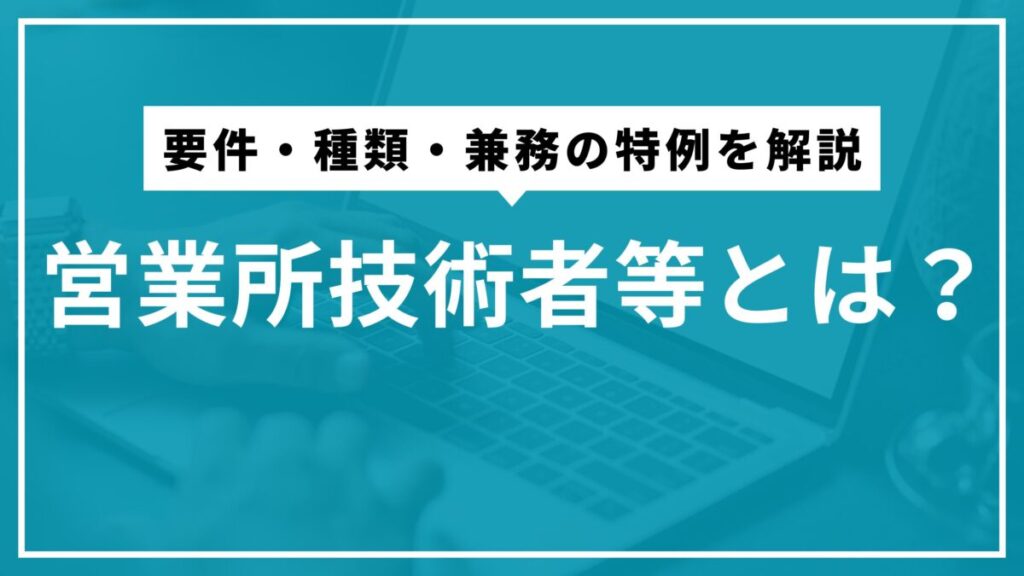
建設業許可を取得・維持するためには、すべての営業所に「営業所技術者等」を専任で配置することが法律で義務付けられています。
なお、以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、2024年(令和6年)の建設業法改正により、一般建設業許可の営業所技術者等は「営業所技術者」、特定建設業許可の営業所技術者等は「特定営業所技術者」と呼ばれることになり、これらの総称が「営業所技術者等」です。
この記事では、「営業所技術者」と「特定営業所技術者」の概要や役割、資格要件、そして兼務の特例についてわかりやすく解説します。
建設業許可の「営業所」とは?認められるための4つの要件を解説>>
営業所技術者とは?営業所技術者等の概要
営業所技術者等とは、建設業許可を取得・維持するために、すべての営業所に専任で配置することが義務付けられている技術者の総称です。以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、2024年の建設業法改正により、以下の2つに呼び方が変更されました。
- 一般建設業許可の場合:営業所技術者
- 特定建設業許可の場合:特定営業所技術者
営業所に技術者を専任で配置することで、その営業所に技術力が備わっていることを証明し、発注者が安心して工事を依頼できる体制を整えることが目的です。
一般建設業の「営業所技術者」の資格要件
営業所技術者は、一般建設業許可を取得する際に必要となる技術者です。
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
| 資格区分 | 学歴・資格 | 実務経験年数 | 追加条件・備考 |
|---|---|---|---|
| 指定学科修了者 | 高校卒業 | 5年以上 | 在学中に指定学科を修了していること |
| 大学(短大等)卒業 | 3年以上 | 在学中に指定学科を修了していること | |
| 専門学校卒業 | 5年以上 | 在学中に指定学科を修了していること | |
| 専門学校卒業 (専門士・高度専門士) | 3年以上 | 在学中に指定学科を修了し、専門士または高度専門士の称号を有すること | |
| 実務経験者 | 学歴不問 | 10年以上 | 許可を受けようとする建設業に係る建設工事の実務経験 |
| 国家資格者 | 1級国家資格保有者 | なし | 建設業に関連する国家資格(1級) |
| 2級国家資格保有者 | なし | 建設業に関連する国家資格(2級) | |
| 複数業種経験者 | 学歴不問 | 規定による | 複数業種に係る実務経験を有する者として認められる者 |
| 技術検定合格者 | 1級1次検定合格者(○○技士補) | 3年以上 | 大学(短大等)指定学科卒業者と同等扱い ※指定建設業7業種・電気通信工事業は適用除外 |
| 2級1次検定合格者(○○技士補) | 5年以上 | 高校指定学科卒業者と同等扱い ※指定建設業7業種・電気通信工事業は適用除外 |
特定建設業の「特定営業所技術者」の資格要件
特定営業所技術者は、特定建設業許可を取得する際に必要となる技術者で、一般建設業よりも厳しい要件が求められます。
特定建設業では、下請けに総額5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事を発注することがあるため、下請けを適切に指導・監督できる高い技術力が必要となります。
特定営業所技術者の資格要件は以下の通りです。
| 資格区分 | 資格・経験 | 詳細要件 | 指定建設業7業種での適用 |
|---|---|---|---|
| 国家資格者 | 1級国家資格保有者 | 建設業に関連する国家資格(1級) | ○ 適用可能 |
| 指導監督的実務経験者 | 一般建設業の営業所技術者要件を満たす者 | 請負代金4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的実務経験 ※発注者から直接請け負った工事が対象 | × 適用不可 |
| 国土交通大臣認定者 (大臣特別認定者) | 特別認定講習合格者または大臣考査合格者 | 指定建設業7業種に関する特別認定講習の効果評定合格者 または国土交通大臣が定める考査合格者 | ○ 適用可能 |
※指定建設業7業種:土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園
専任要件と法改正による兼務の特例
営業所技術者等は、原則としてその営業所に常勤し、専らその職務に従事する「専任」の者でなければなりません。
しかし、2024年の建設業法改正により、人材不足の解消を目的として、以下の要件をすべて満たす場合に限り、営業所技術者が工事現場の技術者(主任技術者・監理技術者)を兼務できるようになりました。
- 請負金額: 1億円未満(建築一式工事は2億円未満)
- 兼任現場数: 1現場のみ
- 距離: 営業所と現場が1日で巡回可能な距離であること(移動時間がおおむね2時間以内)
- 体制: 施工体制の確認ができるICT環境(Webカメラなど)が整備されていること
- 連絡員: 監理技術者等との連絡調整を行う連絡員を現場に配置すること
まとめ
建設業の許可取得・維持には、営業所技術者と特定営業所技術者の配置が必須です。
2024年の法改正では、呼び方の変更だけでなく、現場の技術者との兼務に関する特例も設けられました。
これから建設業許可の取得を検討されている方は、自社の許可区分に合った技術者要件を正しく理解し、適切な人材を配置することが重要です。
岩手・盛岡の建設業許可は金子行政書士事務所にお任せください!
当事務所では、お忙しいお客様に代わって必要書類の作成から許可行政庁との調整、申請手続きまでを一貫してサポートいたします。
「自分は許可が取れるのか?」「どの業種で申請すればいい?」「費用はいくらかかる?」など、どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
▼法令はこちら
建設業法第7条
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の八第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)